
こんにちは、ふぉあぐらです。
今日は、健康で働くことをテーマとして
自分自身の現在の仕事環境についてお話ししてみようと思います。
① 見過ごされがちな「健康で働く」という奇跡

健康な状態で出勤し、契約上の工数を満たす──
それを“当たり前”として扱う風潮に、最近強い違和感を覚えています。
私の働く現場では、一定の稼働時間を維持することが契約上の前提になっています。
もしそれを下回れば「なんて基準下回ったんだ」と言われ、
逆に上回れば「残業しすぎじゃないか」と心配される。
まるで、人間を一定の稼働量で動かす前提の仕組みです。
一見バランスを取っているようでいて、
実際は「人が常に健康で動ける」ことを前提とした、
とても不安定な構造に支えられています。
② 健康管理は“業務の一部”になっている
だからこそ、健康管理は自己防衛の一部です。
私は毎朝ウォーキングをして体を整え、
食事にも気を配るようにしています。
その結果、ここ2年間は風邪をひいていません。
ただ、それは“努力の成果”であっても、
現場では「それくらいは当たり前」とされてしまう。
40代に入れば、いつ何が起きてもおかしくありません。
健康診断では多少の数値の乱れもあります。
それでも、大きな病気もせず働けていること自体が才能だと感じています。
“健康で働くこと”は成果のひとつのはずなのに、
「予定どおり稼働できること」を前提にされる構造が、
すでに無理を生んでいるのではないかと思うのです。
③ 誰も幸せになれない「構造的なジレンマ」

上層部の立場からすれば、
ライフワークバランスを重視すると、
お客様との契約料が見直され、売上に影響するという現実があります。
つまり、
「働きすぎてもダメ、休んでもダメ」
という、誰も幸せになれない構造です。
現場の社員も、マネージャーも、お客様も、
誰かを責めているわけではないのに、全員が板挟みです。
そしてその板挟みの中で、最も犠牲になっているのは「人間の余白」。
体調や家庭の事情といった自然な変動が許されない職場は、
静かに人をすり減らしていきます。
④ 退任した先輩が教えてくれた現実

私がこの問題をより強く意識したのは、
退任した先輩の現実を聞いたときでした。
理由は、家庭の事情により、契約上の作業量をこなすのが難しくなったというもの。
その方は経験も知識も豊富で、長年チームを支えてきました。
それでも「決められた稼働を維持できない」となった瞬間、
その存在は契約を遂行するには困難になってしまうのです。
「家族を優先したい」という、
ごく当たり前の選択が働きにくさにつながってしまう。
これは個人の問題ではなく、仕組みそのものの欠陥だと感じます。
誰も悪くない。
でも、誰も守られていない。
⑤ “壊れない人だけが残る”職場の危うさ
この構造が続くと、結果的に「壊れない人だけが残る」職場になります。
風邪を引かず、怪我もせず、体調を崩さない人が“優秀”とされる。
けれど、それは単なる運や確率の問題にすぎません。
どんなに気をつけても、体はいつか不調を訴える。
それを許容できない仕組みの中で働く限り、
誰かが静かにフェードアウトしていきます。
本来の「生産性」とは、
人が壊れずに働き続けられることのはず。
健康で働けることを“前提”ではなく、“成果”として扱う社会へ。
そうした価値観の転換こそが、今の時代に求められている働き方だと思います。
⑥ 終わりに:健康を保つことは「成果」である
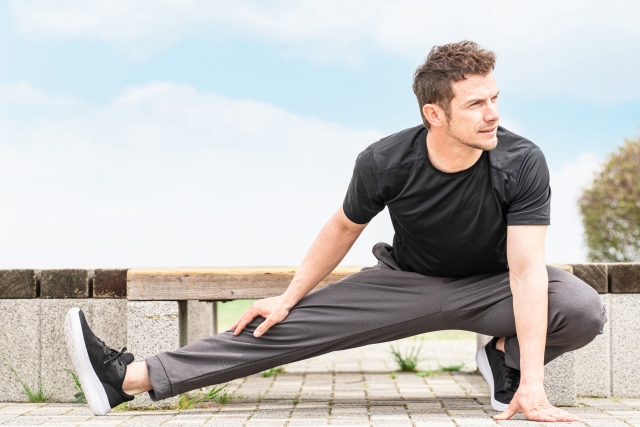
私はこれからも、朝のウォーキングを続け、
食べるものに気を配りながら、しばらくは働いていくつもりです。
健康でいられることは幸運であり、
それを維持する努力は立派な成果です。
だからこそ、
「健康で出勤できる人材がいること」を当たり前にしない。
その意識が、今の働き方に小さな変化を起こすきっかけになるのではないでしょうか。